小説家・村山由佳に聞く【前編】
愛する者との別れと悲しみ

小説家・村山由佳さんの『猫がいなけりゃ息もできない』と、それに続く『命とられるわけじゃない』(共にホーム社)という2つのエッセイは2010年以降、村山さんが都会生活を離れて信州の軽井沢に転居してからの「猫たちとの共同生活」を描いたものである。
というと、生活の機微を題材にした癒やし系ほのぼのエッセイを連想する人が多いかもしれないが、両書には「父の死」、「愛猫の死」、「母の死」などの衝撃と悲しみが描かれたヘビーな告白の書でもあるのだ。
そこで今回は、彼女が小説家になったいきさつから話を聞いていくとともに、大事な存在(猫含む)を失ったあとの死生観などについて、語っていただきたいと思う。
記事は前編と後編、2回に分けて配信していきます。

- 村山由佳(むらやま・ゆか)
1964年、東京都生まれ。立教大学文学部卒。会社勤務などを経て作家デビュー。1993年、『天使の卵――エンジェルス・エッグ』にて小説すばる新人賞を受賞して小説家デビュー。2003年、『星々の舟』で直木賞、2009年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞を受賞。2020年9月に上梓した『風よ あらしよ』(集英社)では、新境地である歴史小説に挑み、第55回吉川英治文学賞を受賞した。
「恋愛」を描くことで、「人間」を描いている
村山さんが「小説家になりたい」と思ったのは、いつごろなんですか?
村山
小さいころ、スイーツ好きの子が「ケーキ屋さんになりたい」と卒業文集などに書いたりするように、本を読むのが大好きだった私は「お話をつくる人になりたい」と思っていました。
とはいえ、それを職業にするという発想はなくて、そのことを意識したのは、最初の結婚をしたときです。専業主婦になって、家の中で働ける仕事って何だろうと考えて、「新人賞に応募して賞金を稼ぐ」という選択肢が初めて目に入ってきたんです。
何度かの応募を経て、小説すばるの新人賞をいただいたのが29歳のとき。受賞作『天使の卵──エンジェルス・エッグ』(集英社文庫)がデビュー作になりました。
小説家という職業は村山さんにとって、「向いている職業」だったのでしょうか?
村山
社会人になって、不動産会社や塾講師の仕事をしてきましたけど、どちらも1年半以上は続かなかったので、小説家デビューして、それらを超える期間がたったとき、「おお~っ、続いてるぞ」と感動したのを覚えています。
ただ、デビュー当初は読者や編集者が投げてくる球を無我夢中で打ち返し続ける日々でしたから、ゆっくり立ち止まって「どんな小説家になるべきか」といったことを考える余裕はあまりなかったですね。
幸いなことにデビュー作は多くの人に支持されましたけど、その反面、求めに応じて「切ないラブストーリー」というテイストの作品を作り続けることは、それなりに大変な作業でしたから。
恋愛というのは、誰もが経験することですから、「面白い恋愛小説」を書くのはとても難しい作業なんでしょうね?
村山
そうなんです。ミステリーというジャンルは、殺人事件がよく描かれますが、「人を殺したときって、こんな気持ちにならないよね」なんて文句をつける人はほとんどいませんよね。
それに比べて恋愛小説の場合、恋愛観や道徳観、価値観などは人それぞれですから、多くの人に説得力のある感動を与えられる物語を作るには、それなりの工夫が必要です。
ですから、経験を積み重ねていくうち、「恋愛小説」という枠組みではなく、「人間を描く」ことを意識するようになっていったように思います。
どういうことかというと、人間の心の針がレットゾーンに振りきれる瞬間を描くということ。ある人はそのために世界中を旅する冒険小説というジャンルを選ぶかも知れないし、別のある人は、空想を自在に広げたSF小説を書いたかもしれない。私にとっては、それが恋愛小説だったわけです。
「自分が経験したこと」が小説になっていく
「人間を描く」というのは、どういう作業なのでしょう?
村山
人を殺したことのない人でもミステリーが描けるのは、その作家の想像力に負うところが大きいと思いますが、私の場合、デビュー作から一貫して「自分が経験したこと」を題材にすることが多いです。
それは、デビュー直後に書いた『おいしいコーヒーのいれ方』シリーズのように、男性を主人公にした小説についても同じことが言えます。
男性作家の中には「自分は女性心理がわからないから、女性を主人公にした作品は書かない」と言う人もいますが、村山さんは違うのですね?
村山
実際、私の体の中には、「男子」がいるんです(笑)。
もともと性格が男っぽいというわけではありませんが、かつて「女子」として経験した恋愛を見つめることで、「男子」が見えてくるんですね。その「男子」が成長して「おじさん」になることはなく、時が止まったまま真空パックされているのは、そのせいだと思うんですけど。
過去の記憶を生々しく思い出す能力は、小説家として大事な能力でしょうね?
村山
そうかもしれませんね。私の中で過去の記憶は、くっきりとした映像として残っていますし、そのときどんなことを言ったのか、どんな気持ちになったのかということは鮮明に保存されています。
ただ、これは女性には当たり前の能力なのかもしれないですね。男女でケンカになったとき、「あのときあなたはこう言った」と過去の記憶を引っ張り出して相手を批難するのは、たいていの場合、女性ですよね(笑)。
まぁ、私の場合、そのような記憶力が小説を書くにあたって役に立っていることは間違いないと思います。

「主婦が作家になるのはむずかしい」という予言
実体験を題材にして小説を書くということは、周囲の人を傷つけることにつながりはしないでしょうか。例えば、「不倫」をテーマにした『ダブル・ファンタジー』は、離婚したからこそ、書けた作品だったのではないですか?
村山
書き始めたころは、まだ離婚していませんでしたけど、本が出版されるときには確かにそうなっていましたね。
私はこれまで2回、離婚を経験していますが、最初の離婚については新人賞の授賞式の日、選考委員のひとりである大御所作家に予言めいたことを言われていたんです。
「おめでたい日に嫌なことを言うようだがね」と前置きして、「誰にでも、自尊心というものがあるからね。あなたがこれから作家として売れれば売れるほど、今のご主人と仲良くやっていくのはおそらく難しくなっていくよ」と。
そう言われたとき、理屈としては理解したものの、「ちょっと気をつければうまくやれる」と思ってました。でも、『ダブル・ファンタジー』を書いていたときの私は、予言のほうが正しかったことを身に沁みて実感していました。
授賞式の場面は、『放蕩記』にも描かれていますが、母娘の確執をテーマにしたこの作品もまた、お母さんが認知症にならなければ書けなかった作品だったようですね?
村山
そうですね。母に読んでもらうつもりで、洗いざらい書いたほうが本物の小説になったのかもしれないと思うこともありますが、母を傷つけることがわかった上で書くというのは、かなりの難事業になったでしょう。
「作家の家族をやっていくのは大変デスネ」という父のひと言
『放蕩記』は、どんなきっかけで生まれたのですか?
村山
『ダブル・ファンタジー』を書いていたとき、担当編集者が主人公の奈津のキャラクターについて「同年代の夫をこんなに恐れるのは、決して普通ではない」と語ったことがひとつの気づきにつながったんです。
奈津は私自身を投影した登場人物でしたから、脚本(現実には小説)を書きながら、そのことで夫を怒らせないようにビクビクしていた気持ちに嘘はないんですが、それが「普通ではない」と言われたことに新鮮な発見をした気がしました。
そして、その気持ちのルーツをたどっていくと、幼いころからの母との関係に結びついていったんです。
母が思い描いている「いい子」でいなければ愛されなかった結果、相手の機嫌が悪くなりそうになると衝突を避けて自分のほうから「ごめんなさい」と言ってしまう。そういう関係性は当初、私と母との間で生まれたものでしたが、同じことを最初の夫との関係でも繰り返していたんですね。
『放蕩記』は村山さんにとって、「書かざるを得なかった作品」だと言えそうですね。
村山
それと同時に、堅い岩盤を掘り進んでいくようなしんどい作業でした。でも、真剣に取り組んでいけば、その先には得がたい鉱脈があるはずだという予感がありました。
それは、どんな鉱脈でしたか?
村山
ひとことで言えば、私と母との関係性に名前がついた、ということですね。
だからといって、書く前と書いた後で私の心がたくましくなったとか、新しい自分に生まれ変わった、なんてことではありません。
でも、名前のないものって、必要以上に怖く感じたりするものじゃないですか。ですから、『放蕩記』という長い小説を書きあげたことで、それまで考えるのさえ怖かったことに名前がついて、本棚にしまっておけるようなものになって、ちょっとはラクになった気はします。
作品を読んだご家族の反応は、いかがでしたか?
村山
父は「作家の家族をやっていくのは大変デスネ」と言っていました。父の口調を再現しようとすると、語尾がカタカナになるんです(笑)。表面的には笑っていても、「やれやれ」という思いが伝わってくるような苦笑いですね。
母との関係で私がいちばんつらい思いをしていたのは、10歳年上の兄が就職して実家を出てしまい、当時、高校生だった私1人で母と対峙しなければならなくなってからなんですが、その兄からは「やっと俺にも家族の全貌が見えた気がする。お前も大変だったんだな」とねぎらいの言葉をもらいました。

父の死は、突然の別れだった
ところで、村山さんが2018年10月に発表した『猫がいなけりゃ息もできない』と、2021年3月の『命とられるわけじゃない』(共にホーム社)は、どちらも小説ではなく、エッセイですが、両書には「父の死」、「愛猫の死」、「母の死」というヘビーな出来事が描かれていて、あたかも小説を読んでいるかのようにドラマチックで、心を揺さぶられる魅力があります。どのようなきっかけで書き始めたのですか?
村山
このふたつのエッセイは、ホーム社の文芸図書Webサイト「HB」の連載をもとにしていますが、別にドラマチックな私生活を描くために始めたものではないんです。
当初は信州の軽井沢にある、写真スタジオを改造した自宅で猫とともに生活する日々を描いた「暮らしのエッセイ」にするつもりでした。
2005年に書いたエッセイ『楽園のしっぽ』(文春文庫)が千葉県の房総の丘で自給自足していたころの日々を描いたものだったので、それに近いものになるのかなと。
連載が始まった時点で父は亡くなっていましたが、そこで経験したことは『ダブル・ファンタジー』の続編となる『ミルク・アンド・ハニー』という小説にくわしく書いたので、エッセイのほうでは冒頭で軽く触れる程度でしたし。
お父さんとは、突然の別れだったようですね。
村山
そうなんです。母が認知症になって高齢者施設に入所して以来、父は千葉県の自宅でひとり暮らしをしていました。
ある日、たまたま東京で仕事をする機会があって、驚かすつもりで足をのばして訪ねていったら、床にうつぶせで倒れていたんです。
司法解剖の結果、死因は脳幹出血でアッという間の死だったようですが、それが私が訪ねていった2時間ほど前のことだったというのです。私の現在のパートナー(エッセイでは「背の君」と呼んでいます)と「びっくりさせたろか」と相談しての訪問でしたが、逆に私たちが驚かされた結果になりました。周囲の人たちからは「まるで呼ばれたかのようだね」とよく言われますが、私自身、本当にそうだなと思います。
ただ、父は亡くなった時点で92歳でしたので、いつかこういう日が来るだろうと、数年前からある程度の覚悟はしていました。母が施設に入ってひとり暮らしになったときも、「いつか軽井沢で私との同居を提案してみよう」と身内で話し合ったりもしていましたし。
それだけに、最後の日々を一緒に過ごすことなく、父をひとりで死なせてしまったことに申し訳ないという気持ちがあって、父との別れを受け入れるのはなかなかにしんどいことでしたね。


受け入れがたい出来事だった「愛猫との別れ」
『猫がいなけりゃ息ができない』には、序盤を過ぎたあたりで愛猫もみじが扁平上皮癌を患って「余命3カ月」を告げられることが語られます。村山さんにとって、もみじちゃんはどんな存在だったのですか?
村山
真珠という母猫のお腹をさすって産ませた子だったという意味では「我が子」のように感じることもあったし、最初の夫のもとを出奔し、東京で初めて一人暮らしをしたときは「大事な相棒」でした。
それから、私が愛情を注げば、それ以上の愛情を返してくれるという意味では「恋人」でもあったし、落ち込んだり、笑ったりする様子をただそのままに受けとめて、そばにいてくれた点では「保護者」でもありました。
当時、軽井沢の住まいには、もみじの他に銀次、サスケ、楓、それから父と最後まで暮らしていた青磁という計5匹の猫がいましたけど、その中でももみじは特別な存在でした。
その掛け替えのない愛猫が死んでしまうかもしれないというのは、受け入れがたいことだったでしょうね?
村山
正直なところ、しんどさで言えば父の死よりもつらかったです。親を見送るのはまだ人の世の順番ですが、もみじは何しろ私のすべてでしたから。
猫の年齢を人間の年齢に換算する方法は、いろいろあるようですが、おおまかに言えば最初の1年で約18歳になり、その後は年に4、5歳ずつ年齢を重ねていくそうです。
その計算で言えば、17歳のもみじは人間年齢で90歳前後。
ですから、お別れしなければならない日が近づいていることはわかっているつもりだったけど、「でも、今じゃない」とそのことを考えるのを避けてきたように思います。
人間にしても猫にしても、「命には限りがある」というのは事実ですが、それを直視するのは誰だってむずかしいですよね。
村山
幸いなことに、「余命3カ月」を生き延びて、10カ月というお別れの期間を過ごすことができたのは何よりでした。まさに、天から与えられた濃密な10カ月間でしたね。
悲しみは、ふとしたときに同じ強さでやってくる
10カ月後にもみじちゃんが亡くなったとき、どんな悲しみがありましたか?
村山
私が恐れていたのは、もみじを失ったとき、半狂乱になって何日も泣き続けたり、自分が自分でなくなった気がして仕事や生活を放棄してしまったりするのではないかということでした。
でも、いざその日を迎えてみると、意外なことに「もみじの不在」を冷静に受けとめている自分がいました。もみじのことをよく知っている編集者が訪ねてきてくれたときは涙も流しましたけど、普通に笑顔で会話をしていましたし、仕事をしているときは集中してそのことを忘れているかのようでした。
仕事には支障が出なかったんですね?
村山
作家には、締めきりというものがあります。「悲しくて原稿を書けません」なんて言っていられないので、父が亡くなったときでさえ、棺の横で原稿を書いてました。
ただ、いざ原稿を書き終えて、編集者に送った途端、父やもみじが「もういないんだ」という事実を急に突きつけられた気がしてドッと悲しみが押し寄せてくるんです。
しかも、その悲しみはずっと同じ強さでやってくるんです。悲しみというのは、時が経てば自然に薄まっていくものだと思っていたけど、そうではないのだということを私は知りました。
もちろん、そのときに流れる涙の量は少しずつ減っていくんですけど、それは悲しみが薄まったからではなくて、それを受けとめる心のほうが強くなって耐性が生まれたという感じ。
人によって悲しみの受けとめ方はそれぞれだと思いますが、私の場合、悲しみはそんな風に簡単に薄まるものではなく、ふとしたときに顔を出すような存在でした。
話しづらいお話を赤裸々に語っていただいて、ありがとうございます。その悲しみがどう癒やされていったのかについては、後編のインタビューでじっくりお聞きすることにしましょう。

もみじ ♀17歳 三毛
男を見る目のない作家のかーちゃんに付き添ってあちこちを転々とし、終のすみかは長野県軽井沢町。半世紀も猫を飼ってきた飼い主をして「こんなに猫らしい猫を見たことがない」と言わしめる、村山家のお局様。なぜか関西弁。
後編記事はこちら→ 村山由佳インタビュー【後編】 元気に楽しく生きる方法
村山由佳の猫エッセイ、待望の新刊!
『命とられるわけじゃない』

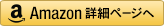
- 著者:村山由佳
- 出版社:ホーム社
- 発売日:2021年3月26日
- 定価:1,650円(税込)
父、愛猫〈もみじ〉に続いて、確執の深かった母を亡くした著者。その母の葬儀で、1匹の猫と出会う。小さなその猫が、止まっていた時間をふたたび動かし……。
「〈後悔〉と〈愛惜〉とは別のものだ」
「愛情は、限られた食糧ではない」
「冷静に考えれば、年を重ねてから楽になったことのほうがずっと多い」
「譲れないことも、許せないことも、人生に一つか二つあれば充分」
「どれほどしんどく思えても、生きてゆく途上で起こるたいていのことは、そう――とりあえず、〈命とられるわけじゃない〉のだ」
今がしんどい人、老いゆく心身に向き合う人、大切なものを失った人、親との関係に悩む人、そして猫を愛するすべての人に贈る1冊。
愛らしい猫たちや美しい軽井沢の写真も多数収録。
この記事について報告する


