小説家・村山由佳に聞く【後編】
元気に楽しく生きる方法

村山由佳さんのエッセイ『命とられるわけじゃない』には、前作『猫がいなけりゃ息もできない』で語られた「父の死」、「愛猫の死」に引き続いて起こった「母の死」が描かれている。
インタビュー後編では、そのいきさつについて語ってもらうとともに、自らの「老い」について、そして「死生観」についても話を聞いてみよう。
50代半ばを過ぎた小説家・村山由佳は今、どのような境地にいるのだろうか?
前編記事はこちら→村山由佳インタビュー【前編】愛する者との別れと悲しみ

- 村山由佳(むらやま・ゆか)
1964年、東京都生まれ。立教大学文学部卒。会社勤務などを経て作家デビュー。1993年、『天使の卵――エンジェルス・エッグ』にて小説すばる新人賞を受賞して小説家デビュー。2003年、『星々の舟』で直木賞、2009年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞を受賞。2020年9月に上梓した『風よ あらしよ』(集英社)では、新境地である歴史小説に挑み、第55回吉川英治文学賞を受賞した。
3年間続いた「見送る春」
お父さんが急逝したのは2017年4月のことで、愛猫もみじちゃんが逝ったのが2018年3月。そして、2019年4月にはお母さんが亡くなったんですね。
村山
そう、「見送る春」が3年続いたわけです。
母が亡くなったのは、お世話になっている南房総の施設から「いつもと様子が違う」という連絡が入ってから1週間後のことでした。
母が施設に入ったとき、「母は認知症になって、もう私のことさえ誰なのかわからなくなってしまう」ということを受け入れたことが最初のお別れだったように思います。ですから、2度目のお別れは自然に受け入れることができました。
このときは何よりも、母を最後まで世話をしてくださった施設の方々への感謝の気持ちでいっぱいでした。
その施設には、母のお気に入りの若い男性スタッフがいて、病院からやってきた看護師さんがベッドから移動させようとすると「痛い、痛い」と叫んで嫌がるんですが、その男性スタッフの方がやってくるとゴキゲンで体を預けていたんです。
認知症の母とそれだけ深い信頼関係を築くまで、どれだけ多くの献身的な奉仕があったかと思うと、本当に頭が下がるばかりでした。
新しい出会いが「心の穴ぼこ」を埋めてくれた
ただ、そんなお母さんとの別れは、新たな出会いを村山さんにもたらしたそうですね。どんな出会いだったのですか?
村山
母のいる施設からの連絡を受けた後、1週間ほど実家に滞在していたんですが、ある日、ベランダのところに一匹の猫が来たんです。
小柄なシャム系の雑種らしい、かわいらしい猫で、思わず「にゃぁお」と話しかけていました。そのときは、ものの1分ほどで目の前から離れていきましたが、その後、母の葬儀を実家で行うことになって、再会したんです。
葬儀の前日、これまで両親がお世話になっていたご近所にあいさつをするため、少し離れたお隣のYさんのお宅を訪ねたときでした。あのときの猫が、道路と畑の境目のところにうずくまっているのが見えました。
そして、その猫が私に気づいた途端、まっすぐに駆け寄ってきて私に甘えてきたんです。まるで、私が来るのをずっと待っていたかのように。
くわしいいきさつはエッセイに書きましたけれど、本当に奇跡としか思えないようないくつかの偶然が重なって、その猫はうちの子になりました。
新たな家族になったその猫は、背中やお腹の毛がしっとりと柔らかいことにちなんで「絹糸(通称・お絹)」と名づけました。
愛猫もみじとの別れを描いた前作『猫がいなけりゃ息もできない』は、次の4行の詩で締めくくられています。
もみじ、もみじ、愛してる。
早く着替えてまた戻っておいで。
そうしたら、私にはきっとわかる。
あんただってことが、きっと、わかる。
お母さんの葬儀をきっかけにして出会った猫との出会いは、この言葉につながるのでしょうか?
村山
そうだといいなとは思いますけど、お絹がもみじの生まれ変わりだと感じるのは人間側の理屈ですし、お絹はお絹ですから、あえてそう考えないようにしています。
それから、この話をすると「亡くなったお母さんが、新しい出会いを呼んでくれたんですね?」と指摘されることもあるんですが、それについては「いえ、違います」と否定しています。それとこれとは話が別、ということが実感としてありますから。
ともあれ、もみじの死による悲しみは完全に消えたわけではないけど、それによって生じた「心の穴ぼこ」のかなりの部分をお絹が埋めてくれたのは確かなことです。
今、一緒に暮らしている夫は、「もみじがおらんようになってからずっと、お前、笑(わろ)てても笑てへんみたいやったけど、今は顔つきが全然ちゃうがな」と言ってくれますけど、お絹との出会いはそれくらい大きな意味を持つことだったんです。

「老い」を経験して、許せることが多くなった
ところで、『命とられるわけじゃない』の終盤には50代半ばになったご自身の「老い」を実感する様子が描かれていますね?
村山
私は長兄と13歳も年が離れた末っ子なので、「両親との別れ」を比較的早めに経験したわけですが、そのせいで余計に自分自身の「老い」というか「衰え」を意識させられる結果になったのかもしれません。
まず、肉体的な衰えについては、50肩で腕があがらなくなり、それをかばうあまりに腱鞘炎になったりしました。それから、徹夜もできなくなってきたのは、体力勝負で仕事の難関を乗りこえてきた私にとっては情けない状態でした。
でも、そんな状態に必要以上に悲観的にならず、「まぁ、いいんじゃね」と自然に受け入れられたのは、年を重ねることによって楽になったことが増えたからだと思うんです。
例えば、今の私の体型について言えば、若さを意識していたころなら、とっくに「ダイエットしなきゃ」と焦っているはずなんですが、「無理して痩せたかて、身体こわしたら元も子もあれへん」というパートナーの言葉にすっかり甘えたままにしています。
思うようにいかないからといって、頑張りが足りないと自分を責めたら、どんどんしんどくなるばかり。「老い」を意識するようになって、そんな風に自分を許すことができるようになったのは、ひとつの進歩だと思っています。

「静かなる無頼」の父が遺した言葉
そんな村山さんの心境は、エッセイのタイトルでもある「命とられるわけじゃない」という言葉にもよく表れていますね。
村山
私のオリジナルの言葉ではなくて、父の言葉なんですけどね。
例えば、母がどうでもいいことに腹を立てたり、考えても仕方のないことを気に病んだりする場面で、たぶん母をなだめるつもりで「ま、ええではナイカ。命とられるわけでなし」と飄々とした口調で言っていました。
その結果、母の怒りをますます燃え上がらせたりしていましたが、そんな父が私は大好きでした。
もともと父は、見栄を張って自分をよく見せようとか、人と競って優位に立とうとか、そういう欲をいっさい持たない人でした。おそらく、赤紙一枚で一兵卒として戦争に召集され、終戦後は4年間もシベリアに抑留された経験から来る「諦観(ていかん)」がそうさせていたのかもしれません。
父は亡くなるまで喫煙の習慣を捨てませんでしたが、70歳を過ぎたころ、母にそのことを咎められ、禁煙を迫られたことがありました。そのとき、父はこう答えたんです。
「死ぬとき健康でどうする」と。
何だか笑っちゃうような理屈ですけど、父らしい言葉だなと今でも強く印象に残っています。父にキャッチフレーズをつけるとすれば、「静かなる無頼」ということになるのかな(笑)。
デビューから27年目の「初めての挑戦」
村山さんは、2020年9月に発表した『風よ あらしよ』(集英社)で権威ある吉川英治文学賞を受賞しました。作家には定年がないと言いますが、ますます活躍の場を広げられているという印象があります。
村山
これまで書いてきた作品の中で、自分にとっても目盛りとなるような重要な作品がいくつかありますが、『風よ あらしよ』は間違いなくそのひとつと言える作品だと思います。原稿を書き上げ、本になった瞬間、初めて「本当に胸の張れるものが書けた」という実感がありました。
伊藤野枝という実在の人物を主人公にしたこと、明治から大正にかけての100年前の時代を舞台にしたことなど、そもそもが初めてづくしの試みでした。
ただ、評伝小説でありながら、自分の体験がこれほど活きてくることに自分でも驚きました。野枝は恋多き女で、激情に従って夫のもとを去り、無政府主義者の大杉栄の事実上の伴侶になったりして、最後は大杉とともに処刑されて28年の短い人生を閉じるんですが、虐げられた女性が声を上げられなかった時代に自らの正義を貫き通そうとする姿勢には大いに共感させられたし、行動のはしばしに「あ、私はこの感情をよく知ってる」と思うような発見も少なくありませんでした。
それは、今まで登ったことのない高さの山に登ったような体験で、そこから見えた、さらに高い山の景色に向かってこれからも書き続けていかなければならないという思いを新たにしました。
小説家デビューから27年たっても、まだ経験したことのない新しい発見があるんですね。
村山
本当にそう思います。私は本来、飽きっぽい性格なんですけど、書く作品ごとに新鮮な発見があって、だからこそ、これまで何とかやってこられたのだと思います。

妥協できない自分ルール、それは「ズルをしない」
最後に、読者のために「元気よく生き続けるコツ」をアドバイスしていただけますか?
村山
生活面では、あらゆるところに妥協していますので、大したアドバイスはできないと思いますが、文章を書くことに限って言えば、ひとつだけ妥協しないでいようと決めていることがあります。
それは、「ズルをしない」ということ。
たとえ、そのズルが人にばれない、自分だけがそれとわかるズルだとしても。
どういうことかというと、書こうとしても、うまく書けそうもない気がして、あえてそこには触れずに曖昧にしておくとか。
寝不足が続いてしんどいとき、「こういう結末にしておいたら、とりあえずの形はつく」という線が見えてくるんです。長く文章を書いていると、そういう知恵や技術は知らず知らずのうちに身についてしまうもので。
でも、その先に光が見えていて、そこにたどり着けばきっといいものになるとわかっているのなら、決してあきらめない。そういうことです。
なぜなら、そうやってズルをしてゴールテープを手前に引き寄せたとしても、あとで必ず後悔するからなんです。その作品が酷評されたりしたときは、たぶん、耐えがたいほど悔しい思いをするだろうし、逆に褒められたとしても手放しで喜べないでしょう。
逆に、「ズルをしないで最後までやりきった」という手応えがあれば、どんな酷評も受け入れられるし、褒められたときは心から嬉しくなります。
ちっぽけなものでもいいから、自分の中にそんなちょっとした「誇り」のようなものを持っておくと、人生はだいぶ楽しくなる。私はそう思います。
興味深いお話、どうもありがとうございました。

絹糸 ♀2歳 シャムMIX
通称・お絹。村山母の葬儀の晩、はるばる南房総から軽井沢に連れてこられた。ふだんはかーちゃんのストーカー、張り込みと尾行に1日のほぼすべてを費やし、いざ抱っこされると嬉しさのあまりよだれを垂らす癖がある。顔も体も丸い。鳴き声は「うん⤴」「うん⤵」。
村山由佳の猫エッセイ、待望の新刊!
『命とられるわけじゃない』

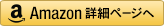
- 著者:村山由佳
- 出版社:ホーム社
- 発売日:2021年3月26日
- 定価:1,650円(税込)
父、愛猫〈もみじ〉に続いて、確執の深かった母を亡くした著者。その母の葬儀で、1匹の猫と出会う。小さなその猫が、止まっていた時間をふたたび動かし……。
「〈後悔〉と〈愛惜〉とは別のものだ」
「愛情は、限られた食糧ではない」
「冷静に考えれば、年を重ねてから楽になったことのほうがずっと多い」
「譲れないことも、許せないことも、人生に一つか二つあれば充分」
「どれほどしんどく思えても、生きてゆく途上で起こるたいていのことは、そう――とりあえず、〈命とられるわけじゃない〉のだ」
今がしんどい人、老いゆく心身に向き合う人、大切なものを失った人、親との関係に悩む人、そして猫を愛するすべての人に贈る1冊。
愛らしい猫たちや美しい軽井沢の写真も多数収録。
この記事について報告する




