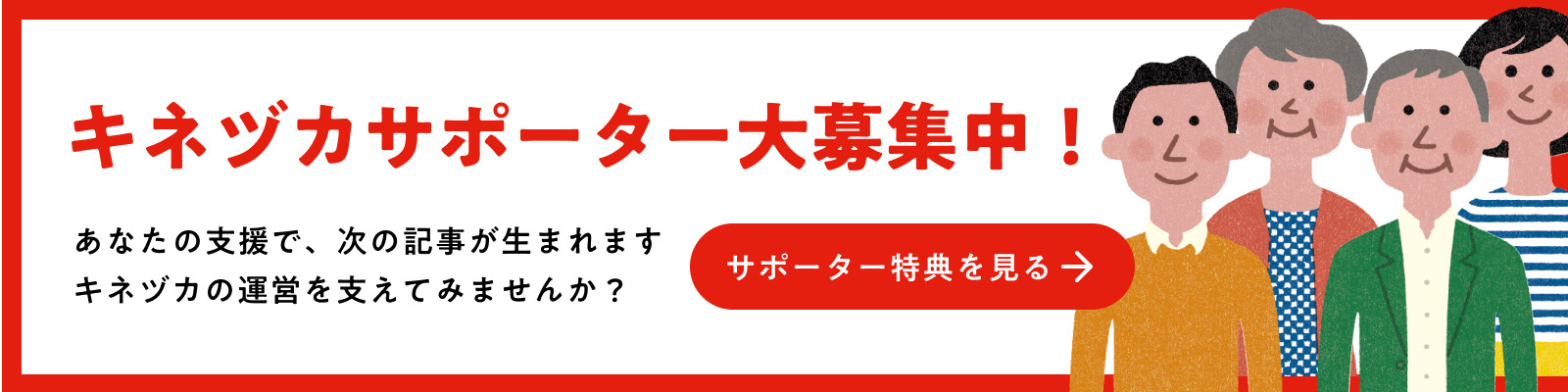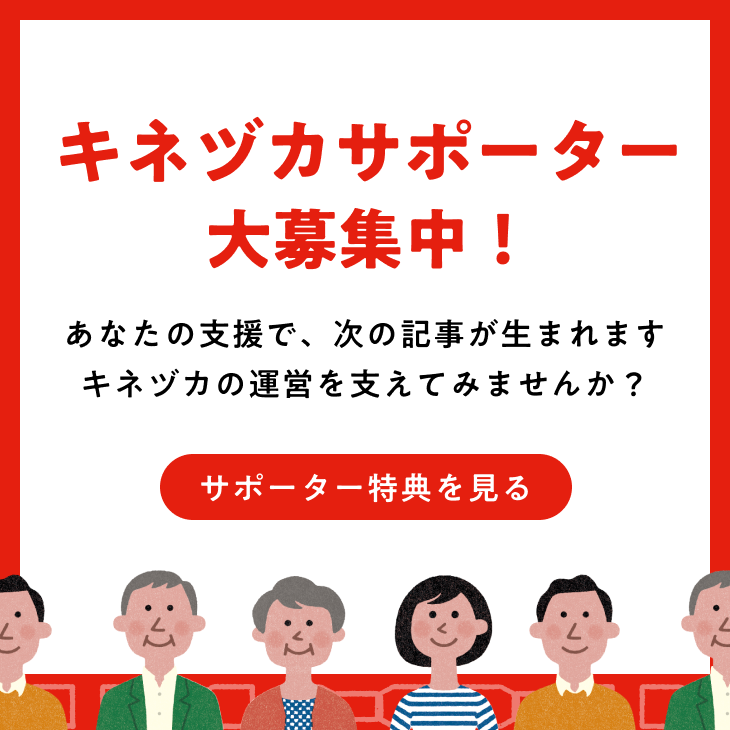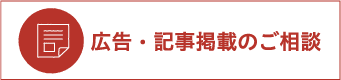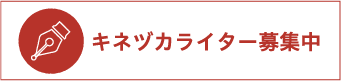変わりゆく定年制度。いつまで働くかは自分次第?

60歳から65歳へ? 法改正の内容
年金支給開始年齢の引き上げを受け、2013年4月に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。60歳を過ぎていても、希望者は原則全員継続して雇用することを企業に対して義務付けるという法改正です。
これにより日本の企業は「定年制度を廃止する」「適用年齢を65歳に引き上げる」「希望者全員を再雇用する」以上3つのいずれかの対応をとる必要があります。
ちなみに継続雇用や再雇用において、企業が常識的な範囲内での契約条件を提示し、社員側の希望と折り合わずに雇用がなされなかったという場合に罰則規定はありません。
しかし、双方のニーズが合致すれば、慣れた職場で仕事を続けられることは生活を支える手段としてベストな選択の一つです。知識と経験のある従業員を手放さずに済むことは企業側にもメリットがあります。
また、同じ業務で再雇用した場合の給与カットは違法とする判決が東京地裁で下されたことも、再雇用を考える方は覚えておきましょう。
再就職か起業か? いくつもの道
とはいえ年金支給額が満額となる65歳に達すれば、多くの場合退職を余儀なくされます。健康なうちは働き続ける意思があるなら、再雇用にこだわるよりも、年齢制限のない職場への再就職にそなえて準備を始めましょう。
やさしい道ではありませんが、培ってきた経験とスキルを活かし、雇用形態にこだわらなければ選択の幅は広がります。定年による離職後に、それまでの職種と大きく異なる業界に飛び込む例は比較的女性に多く、柔軟性が問われることがうかがえますね。
一方、独立起業を夢見る男性は多いのではないでしょうか。自分の裁量ですべてを取り決められる、真に定年制のない労働形態は究極の再就職とも呼べるでしょう。
現職のスキルを活かすにせよ、趣味や得意分野を基盤とするにせよ、安定して生活費を得るためには情報収集や資金繰りに始まり入念な準備が必要となります。リスクはすべて自分で背負う、それが自営業であるということは忘れてはいけません。
生きがいにつながる仕事を
そのほかにも、パートタイムやアルバイトで短時間のみ働く、シニアに門戸を開いた人材派遣会社に登録する、はたまた農業を始めてみるなど、仕事の選択肢は千差万別です。
社会制度が目まぐるしく変遷を遂げ、思い描いていた老後とはだいぶ違う姿を突きつけられているかもしれませんが、ライフスタイルの多様化ととらえることも可能です。
仕事を通じて社会と関わり続けることは、金銭面のみならず生活全般を豊かにしてくれるはずです。前向きに考えて、あなただけのライフプランを立てましょう。
最新更新日 2018.02.19
関連キーワード
この記事について報告する