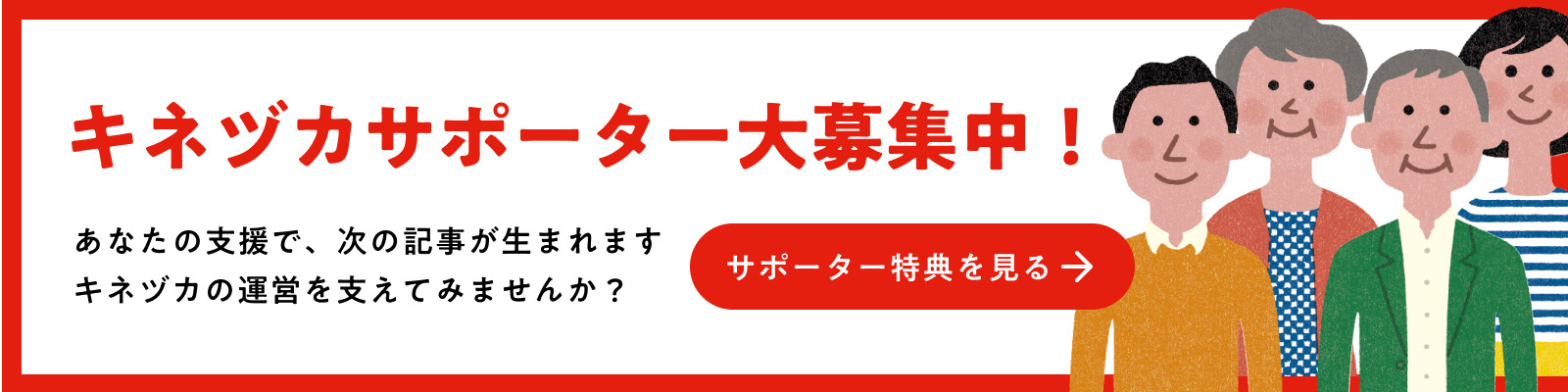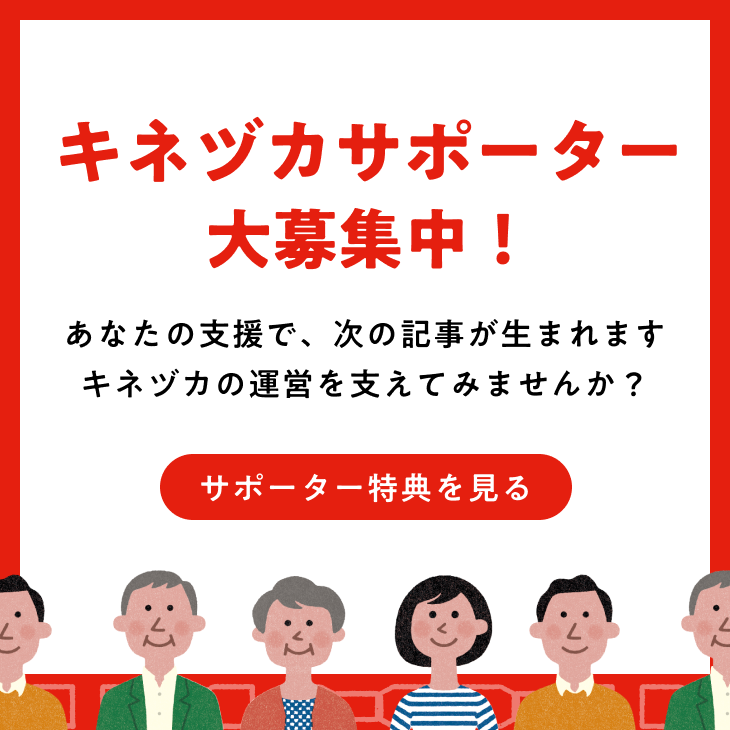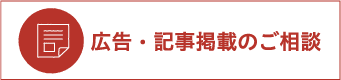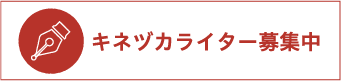おいしいパンをお届け。パン屋さんを開業するには?

息の長いパンブーム到来
現在の日本ではパンも米に匹敵するほど消費量が大きくなっています。
全国にパン屋は約1万軒あるといわれており、グルメサイトや雑誌には新規オープンしたパン屋の情報が数多く掲載されています。実際にパン屋を開業するには何を用意し、どのような手続きが必要なのでしょうか。
意外と高額!初期費用と開業資金
一般的に、パン屋の開業には高額な初期費用がかかります。具体的には物件費、内装工事費、厨房機器費、備品費、広告宣伝費、食材等仕入れ費、当面の運転に必要な費用などです。
このなかで高額なのが物件費です。東京の主要エリアでテナントを借りる場合、家賃の6~20ヶ月程度の保証金が必要となり、これに礼金、仲介手数料、初回家賃が加わります。
契約後に行う内装工事の期間に支払う家賃も事前に用意しておく必要があります。なぜならば、内装工事を行っている間は営業することができないので、売り上げがゼロの状態で家賃を払うことになるからです。
これらのことを考えると、店舗の広さや立地にもよりますが、月々の家賃が50万円程度の物件を借りるとするならば、最低でも500万円程度の物件費が必要になります。
また、手作りパンを焼いて販売するのであれば、専用のオーブンや冷蔵庫を用意しなければなりません。この厨房機器費が高くつくのがパン屋の開業費用が多額になる理由のひとつです。
内装工事費も高額になることがありますが、居抜き物件を借りたりデザインを工夫したりして安く済ませることも可能です。ホームページやチラシを作成する宣伝広告費は10万円程度が目安でしょう。
なお、パン職人を雇う場合は人件費も必要になってきますが、自分でパン作りをするのであればこの費用は不要です。ただし、未経験の場合、専門学校に通って国家資格のパン製造技能士を取得したり、他のパン屋で修行したりして技術を身に付けなければなりません。
以上のことを考えると、トータルで1,000万円、場合によっては2,000万円の開業資金が必要となります。
資金不足ならばフランチャイズもあり
資金が足りなければ、融資制度を利用して不足分を賄うこともできますが、フランチャイズで開店すれば初期費用を安くすることができます。
パン作りの技術やノウハウも学べるので、比較的早く経営を軌道に乗せられるかもしれません。実店舗ではなく、ネットショップで開業すれば300万円程度の資金でオープンすることも可能です。
開業に必要な資格や法手続は?
パン屋を開業するためにしなければならないことは他にもあります。資格の取得もそのひとつです。パン屋を開業する際に必要な資格は、食品衛生責任者、菓子製造業許可、飲食店営業許可の3つです。
食品衛生責任者はパンに限らず食品の製造や加工を行う際には必ず用意しておかなければならない資格ですが、6時間程度の講習を受けることで簡単に取得することができます。
菓子製造業許可はジャムパンやあんパンなどの菓子パンを製造・販売する際に必要な資格で、飲食店営業許可はサンドイッチや総菜パンなどの調理パンを製造・販売したり、イートインスペースを店内に設置したりする際に必要となります。
調理パンのみを販売するのであれば菓子製造業許可は必要ないのかというと必ずしもそうではなく、自治体によっては求められることがあるようです。
法的手続きとして行わなければならないことは、保健所に営業許可を申請することです。これは食品衛生法で定められていることなので、許可なく営業すると違法となります。
また、個人事業主として開業する場合、税務署に開業届をオープン後1ヶ月以内に、青色申告を行うのであれば申請書を2ヶ月以内に提出しましょう。
要となるコンセプト、経営戦略が重要
これまで挙げてきたことは必要最低限のことですが、これらと同じくらい大切なことは事前にしっかりとした経営戦略を練っておくことです。
自分が持っているイメージやコンセプトを思い通りに実現できるのは個人経営の魅力のひとつですが、その結果繁盛するかしないかは経営者の手腕にかかっています。
物件を借りる際にしっかりとリサーチを行う、あたたかみのある内装にして気軽に入れる雰囲気を作る、他店のパンを研究して差別化を図る等々、せっかく苦労してオープンさせた店が短期間で閉店とならないように準備を行うことが何より大切といえるでしょう。
最新更新日 2018.06.09
関連キーワード
この記事について報告する