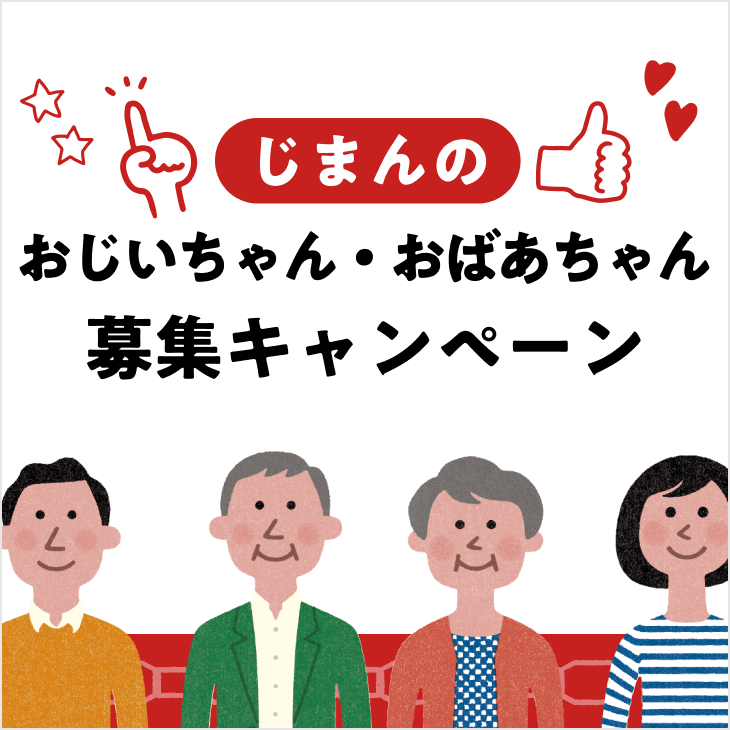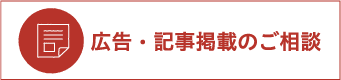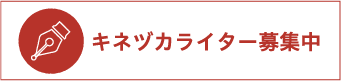定年後の就職はメリットだけではない? 働き続けることのメリット・デメリット

65歳から受け取れる老齢厚生年金の額が増加
日本の社会保障制度は時代とともに変化してきました。1980年代頃までは55歳で定年退職し、60歳から年金を受けるのが一般的でしたが、現在はほとんどの企業が60歳を定年としており、老齢厚生年金の支給開始年齢も60歳から65歳へと段階的に引き上げられています。
定年後は趣味や旅行、ボランティア活動などをしつつ悠々自適な生活を送る人もいますが、現在は政府が少子高齢化による労働力不足への対応の一環として高年齢者雇用促進への取り組みを進めているということもあり、身体が元気であれば定年を迎えた後も働き続ける高齢者が増えています。
働く理由は、退職してヒマを持て余しているから、定年から年金受給開始までの空白期間の生活費を稼ぎたい、社会との繫がりを維持したいなど人それぞれですが、定年後に働き続けることにはメリットとデメリットの双方があります。
定年後の働き方を大きく分けると、それまで勤めていた企業の再雇用制度を利用する、他の企業や業種に再就職(転職)する、自営業として独立する、になります。
新しい企業や業種で第二の人生を送りたいという人は再就職や転職を選択するというのもひとつの手ですが、年齢がネックとなり転職活動にかなりの労力が必要となる可能性があります。
また、独立して会社を立ち上げたり、新しく店を始めたりなども、元手がかかるうえに軌道に乗るまで時間がかかる場合が多く、失敗するというリスクが常に付きまといます。
人脈や技術、強固なビジネスモデルがあれば別ですが、退職金をつぎ込んで起業したのは良いが、失敗して無一文になるということにならないように気を付けなければなりません。
これらのことを考えると、会社員として定年を迎えた場合は再雇用制度を活用するのが無難といます。再雇用制度のメリットは何といっても、慣れ親しんだ会社で仕事を続けることができる点と、転職活動をする必要がないので無給期間や転職に必要な費用が発生しないという点です。
さらに、自営業とは異なり条件を満たせば60歳以降も厚生年金に加入することができるので、加入すれば65歳から受け取れる老齢厚生年金の額も増えるというのもメリットの一つです。
支給額が減額されることもある在職老齢年金制度
一方、定年後に働き続ける際に気を付けなければいけないのは年収によっては老齢厚生年金の支給額が減額されることがあるということです。
在職老齢年金制度と呼ばれますが、正確には厚生年金の被保険者が老齢厚生年金の支給を受ける場合、総報酬月額相当額と年金の月額に応じて年金の一部または全部が支給停止されるという内容です。
総報酬月額相当額とは年金の受給権が発生した月以後の月収に、その月以前1年間における年間賞与を12カ月で割った額を足した金額です。
特別支給の老齢厚生年金が受けられる60歳~64歳の場合、この総報酬月額相当額と年金月額の合計が28万円以下であれば年金は減額されません。
合計が28万円を超えると減額されるのですが、いくら減額されるかは総報酬月額相当額が46万円以下(2017年4月19日現在)か否か、年金月額が28万円以下か否かで異なり、全部で4通りの計算方法があります。
65歳以上の場合は、総報酬月額相当額と年金月額の合計金額が46万円以下であれば減額なし、46万円を超えれば減額です。この場合における金額の計算方法はひとつで、合計金額から46万円を引いた額の半額が減額されることとなります。
たとえば総報酬月額相当額が60万円、年金月額が10万の場合は、2つの合計の70万円から46万円を引いた24万円の半額である12万円が減額されるので、事実上年金は全額支給停止となります。なお、支給停止の基準となる28万円や46万円など金額は毎年見直されることになっています。
ただし、この在職老齢年金制度はあくまでも老齢厚生年金が対象なので、老齢基礎年金が減額されることはありません。また、厚生年金には1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上で、1カ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分3以上などの加入条件があるので、パートや自営業など条件に該当しない雇用形態であれば適用対象外となります。
また、場合によっては定年前よりも給与水準が下がる可能性があることも、働き続ける際に考慮に入れておくべきでしょう。このことについては、再雇用によって賃金が大きく下がった人に助成金を65歳まで支給する高年齢雇用継続基本給付金という制度があります。
60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満に低下した人が対象となる制度で、支給される金額はどの程度低下したかによって異なります。
60歳到達時の61%超~75%未満に低下した人には支給対象月に支払われた賃金の0%~15%が、61%以下に低下した人には15%が給付されます。
ただし、この制度を利用できるのは60歳以上65歳未満の一般被保険者であり、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が5年以上である必要があります。なお、再就職によって賃金が大きく低下した高齢者従業員に対しても、高年齢再就職給付金という同種の制度が用意されています。
このように定年後に働き続けることにはメリットばかりではなくデメリットもありますが、各種の制度を理解したうえで働き方を変えることにより、マイナス面を少なくすることも可能です。
年金の減額についての計算は複雑でわかりにくい部分もありますが、年金事務所に行けばいくら減るのかを計算してくれるので、気になる人は訪れてみるのも良いでしょう。
最新更新日 2018.02.27
関連キーワード
この記事について報告する