俳優、石丸謙二郎に聞く!【後編】
いつも20年後の自分に胸を張れる自分でいたい
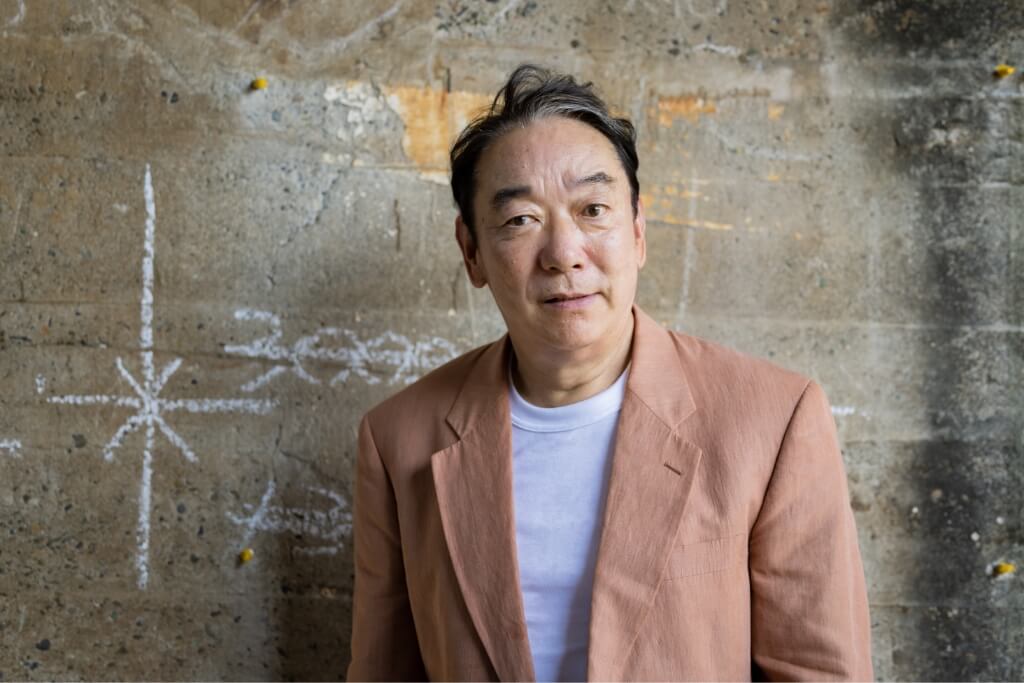
石丸謙二郎さんの「本業」は俳優である。
前編のインタビューでは、ウインドサーフィン、フリークライミング、登山をはじめ、60歳を過ぎて始めたスキー、釣り、ピアノ演奏、墨絵について語っていただいたが、今回はこれまでの俳優人生について、話を聞いてみよう。
20代後半の天才劇作家つかこうへいさんとの出会いから始まって、劇団を離れてからの30代、40代は石丸さんにとって「迷いの時期」だったという。
そんな石丸さんも、50代になってようやく仕事が「楽しい」ものになり、60代からは「おもしろい」と思えるようになったという。
すべての仕事人の励みになる、心熱くなるインタビューだ!
前編記事はこちら→石丸謙二郎インタビュー【前編】1回だけの人生を5倍も10倍も楽しむコツ

- 石丸謙二郎(いしまる・けんじろう)
1953年生まれ、大分県出身。1978年、つかこうへい事務所の公演で俳優デビュー。1987年からテレビ朝日系『世界の車窓から』のナレーションをつとめ、現在まで36年に及ぶ長寿番組に。2018年からはNHKラジオ『石丸謙二郎の山カフェ』のパーソナリティーをつとめるほか、テレビ、舞台、映画と幅広く活動している。
怪しい投資話に騙されてホームレス生活に転落
大分県から上京して、日大藝術学部演劇学科に入学したのは、俳優になるためだったんですか?
石丸
いや、その時点ではまだ漠然としたものでしたね。実際、当時の東京はアングラ演劇が花盛りで、天井桟敷とか状況劇場、黒テントなど、いろんな芝居を観にいったんだけど、ピンときませんでした。田舎者だったし、演劇というものの意味すらわからなかった。
アングラ演劇ではなく、エンターテインメントな演劇がやりたかったんですね?
石丸
そうです、そうなんです。だからニューヨークに行って、本場ブロードウェイで腕を磨いてこようと志を立てて、お金を貯めることにしました。
当時は1ドル360円で、アメリカ大使館からビザをもらうには1万ドルの見せ金を用意する必要があったんです。
前編のインタビューでラブホテルの住み込みのアルバイトを始めた話をしたけど、それ以外に昼間にビルの掃除、夕方からは飲み屋の店員という具合に計3つのバイトの掛け持ちだったから、寝るのは朝10時から午後1時までの3時間だけ。あとはずっと働いていました。
1万ドルといったら360万円。今なら1000万円くらいの価値になるんじゃないですか?
石丸
だから、稼いでも稼いでも、いっこうに目標額に近づく気配がありません。そこで、知り合いに怪しい投資話を持ちかけられて、それまで稼いだカネを預けちゃったんです。
今思えば、見るからに怪しい人でね。シャツの胸ポケットに赤い染みがあったんだけど、あれは競馬新聞に赤い線を引くペンの色だったんだね。
案の定、僕のカネを持ったまま、いなくなっちゃった。
せっかく稼いだお金を持ち逃げされたわけですね?
石丸
応援してくれる仲間が送別会を開いてくれたんだけど、合わせる顔がなかったですよ。
2年間働いて稼いだお金も全部、なくなっちゃったからサーカスのアルバイトを始めて、全国を転々とする生活をおくっていました。住むところがないから、公園で寝たりしてホームレス同然の生活です。
つかこうへい事務所に裏口入学で入団
つかこうへいさんとは、どんなきっかけで出会うんですか?
石丸
つかさんの芝居を初めて見たのは、青山のVAN99ホールで上演された『松ヶ浦ゴドー戒』。入り口にお客さんの行列ができていたので興味を持って見たんだけど、なんておもしろい芝居なんだろうと衝撃を受けました。
だから、友だちがつかさんの『サロメ』というロックオペラに出るという話を聞いて、興味津々で稽古場を見にいくことにしたんです。
3000人のオーディションで選ばれた役者が50人ほど、ズラリと並んでいました。ところが、つかさんも初めて手掛けたミュージカルということで、稽古はうまく進んでいないようでした。
そうこうするうち、「誰か踊れるヤツはいないか」と声がかかって、気がついたら「はい!」と手を挙げていました。
当時からダンスは踊れたんですか?
石丸
身体を動かすのが好きで、ダンスはいろいろと習っていたんです。クラシックバレエやジャズダンス、特にタップダンスには力を入れていました。
オーディションを受けたわけでもないのに、『サロメ』に出演することになったのは、そういうわけがあったんです。その後は、なし崩し的に劇団「つかこうへい事務所」の一員として、次回作の『いつも心に太陽を』の舞台に立ってました。完全な裏口入学だね(笑)。

当時のキャッチフレーズは「脳ミソまで筋肉でできてるヤツ」
つかこうへい事務所では、どんなふうにお芝居を作っていたんですか?
石丸
つかさんの芝居づくりは、とにかく型破り。稽古場には台本がなくて、その場その場でつかさんが即興でしゃべるセリフをオウム返しになぞっていく「口立て」というのをやるわけですけど、1回の稽古が12時間になるなんてのは当たり前。その間、役者はずっと気が抜けません。
例えば、幹になるストーリーがあるとして、稽古場ではそこからいろんな枝葉を伸ばして、いろんなバリエーションを作っていくんです。ときには、「この役はお前がやってみろ」と役を入れ替えたりしてね。
とにかく、つかさんの演技指導というのは、その役者の人間性までもさらけ出させて、それを丸ごと全否定するような厳しいものでした。
「お前は脳ミソまで筋肉でできてるようなヤツだな」というのは、そんな稽古場で僕が言われた言葉のひとつ。
僕は芝居はド下手だったけど、体力だけで乗りきっていたようなものでしたからね。「そのへんで飛び跳ねてろ」と言われれば、30分でも1時間でもぶっ続けで飛び跳ねてました。
台本がないのに、どうやってセリフを覚えるんですか?
石丸
つかさんの「口立て」で覚えたセリフは、稽古が終わっても不思議と忘れないんです。
それは、つかさんがその役者の人間性の深いところまで理解してセリフを与えている証拠でしょう。
だから、つかさんの芝居では、どんなに小さな役にも必ず見せ場があって、嘘のない、血の通ったセリフをしゃべってるんです。上手いとか下手とかを超越した、リアルな魅力、というのかな。
つかさんには、どうしてそのようなことができたのでしょう?
石丸
う~ん、つかさんがスーパー天才だったからとしか、言いようがないなぁ。
数年前、劇団員で、つかさんの原稿アシスタントをしていた長谷川康夫が『つかこうへい正伝-1968-1982-』(新潮社)という本を書きました。
それを読んでみると、当時、ただ怖いだけの人だと思っていたつかさんの、ナイーブで思いやりに満ちた一面があったのを思い出しました。
それは、どんな一面ですか?
石丸
こんなことがありました。ある芝居の公演中、僕の両親が観劇しにくる日があって、それを知ったつかさん、本番の直前で「おい平田(満)、あそこのお前のセリフ、石丸にやれ」と指示してセリフを増やしてくれたんです。
こっちは負担が重くなるから、ありがた迷惑なところもあるんだけど、「親の前でいい格好をさせてやりたい」という親分的な気遣いをしてくれるような人でした。
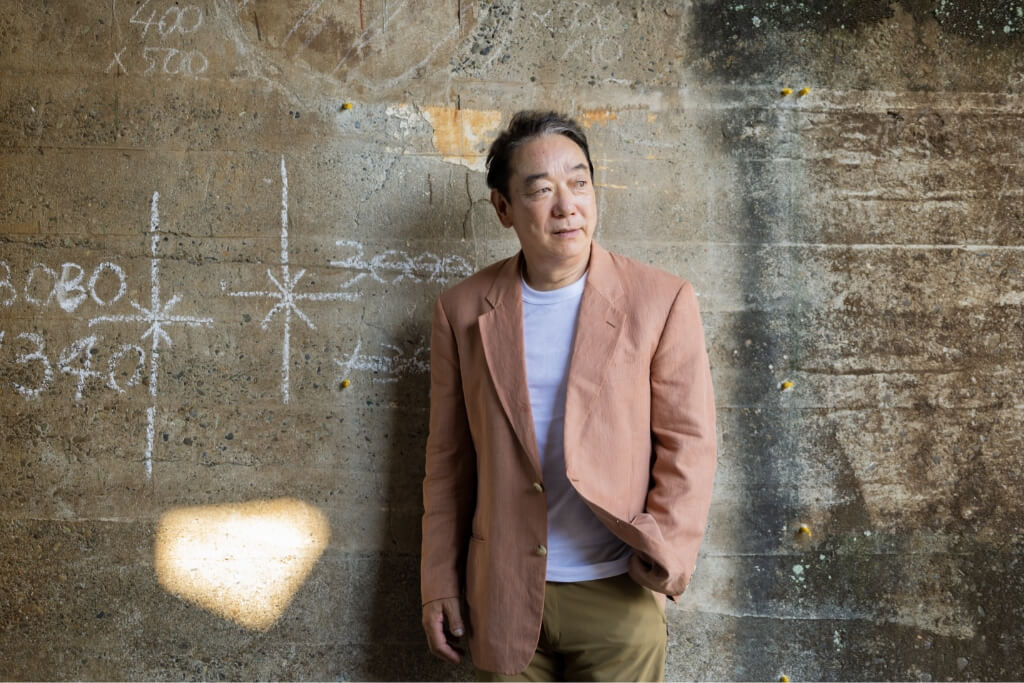
チョイ役だろうが悪役だろうが、何でも引き受けた30代
劇団「つかこうへい事務所」は、石丸さんが入団して5年目にして解散となるわけですが、喪失感は大きかったんじゃないですか?
石丸
そりゃそうですよ。何より困ったのは、台本がなかなか覚えられなかったこと。それまでずっと、つかさんの「口立て」でやってきたから、紙に書いてあるセリフが頭に入ってこないんです。
仕方がないから、自分の声をテープに録音して、ひとり「口立て」で覚えようとしたりね。
セリフに気持ちを入れるのにも、苦労しました。
例えば台本に「君はどこに行くんだい?」と書いてある。
どんな気持ちでこの言葉を言っているのかがわからなくて、そのまま覚えても棒読みになっちゃうんです。試行錯誤した結果、すべてのセリフをいったん大分弁に飜訳するという方法を思いつきました。
「おメエ、なにしよるんかい。どきぃ行くんかい」
そうやって大分弁にして口に出してみると、そのセリフをしゃべっているときの気持ちが心のなかに浮かんで、ああ、なるほどね、と理解できるんです。
劇団に所属していたころとは別の方法で、俳優としての技術を独自に学んでいったわけですね?
石丸
そうです。だから、「頼まれた仕事は絶対に断らない」という方針を立てて、どんな役にも挑戦しました。
チョイ役だろうが悪役だろうが、何でも引き受けて、自分なりの演技を確立しようと必死だった。
いちばん苦手だったはずのナレーションに挑戦
ナレーションの仕事も、その一環ですか?
石丸
そうですね。劇団にいたころは、「石丸は肉体派だから原稿を読ますな」なんて言われるほどだったから、ナレーションの仕事の依頼がきたときは、自分でもビックリしました。
テレビ東京の『おーわらナイト』という、スポーツ選手に密着取材をしたドキュメンタリー番組です。
ところがナレーションなんて初めての経験ですから、何度もNGを出してスタッフたちに呆れられる始末。僕がトチるたび、ガラスの向こうにいるスタッフがげんなりしてくる顔を見るのがツラくてね。
だけど、その1カ月後、番組プロデューサーの網野英夫さんが収録スタジオにやってきて、スタッフに向かって檄をとばしたんです。「石丸を起用したのはオレだ。オレが選んだキャストに文句を言うつもりか。ちゃんとやれ!」って。それ以降、スタジオの空気が一変しました。
当時、テレビ番組のナレーションというと、若山弦蔵さん、矢島正明さん、野沢那智さんといった耳に優しい低音ボイスの俳優が受け持つのが主流だったから、僕の不安定で下手なヴァイオリンみたいな中高音の声に、当時のテレビマンが違和感を持つのは当然なんです。でも、1982年にテレビ東京のドラマ『つか版・忠臣蔵』にたずさわっていた網野プロデューサーは、それを承知で僕にナレーションを担当させてくれたんですね。
その意気に応えなくてはいけないと、僕自身も新しいナレーション表現を切り拓いていくつもりで、番組作りに臨むようになりました。
1987年6月から始まったテレビ朝日系のミニ紀行番組『世界の車窓から』のナレーターに起用されたのは、そのときの経験があったからなんですね。
石丸
そうです。僕に声をかけてくれたのは、初代プロデューサーの岡部憲治さんでした。
当時、岡部さんがイメージしていたのは、「世界を旅する若者」だったそうです。80年代に登場したバックパッカーたちの目線が必要だったようで、すでに33歳になっていた僕は「若者」とは言えない歳だったんですけどね。
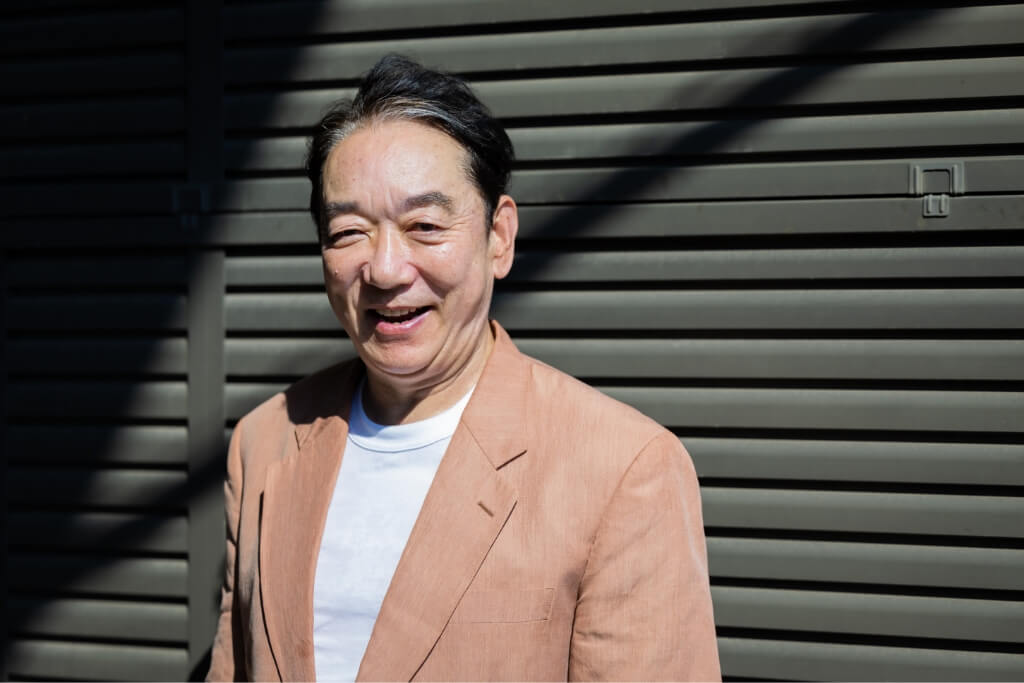
低迷時代を支えてくれた『世界の車窓から』
『世界の車窓から』は、今年の6月に37年目に達していますが、この番組がこれほどの長寿番組になると番組開始から思っていましたか?
石丸
いや、とんでもない。僕自身は、すぐに終わってもおかしくない番組だと思っていました。
放送開始最初の週の収録のことは、今も不思議と鮮明な記憶があるんです。その週は、ロンドンからエディンバラへと向かう旅の紹介だったんですけど、技術の音響さんもいるので、そのときだけ初めてテストをしたんです。
当時、ナレーションというのは、何回もテストをやって、それから本番に行くスタイルだったんだけど、その最初の1回のテストでああしましょう、こうしましょうという指示も受けずに「では、次は本番です」って言われた。
で、この番組は2016年5月2日の回で放送回数が1万回に達して、2023年6月で放送期間も36年になったんだけど、その間、一度もテストというものをしていないんです。
VTRもあらかじめ見せてもらうことのない状態でマイクの前に座って、「本番」が始まるんです。台本はあるけれど、車窓と同じようなサイズのモニターを見ながら、世界を旅した映像に合わせて自分なりのリズムでしゃべっていくだけ。そのスタイルで、ずっとここまでやってきました。
「石丸は肉体派だから原稿を読ますな」という劇団時代のレッテルを、自らの努力で剥がしたわけですね?
石丸
いや、そんなふうに大袈裟に言うつもりはないけど、劇団から離れてからは仕事も不安定で、ときには年収が10万円しかなかったこともあるんです。
でも、『世界の車窓から』で定期的な収入をいただけることになって、何とかやっていけるようになった。そのことは大きかったですね。
これまで、いろんな役者と出会ってきたけど、20代の若いころから実年齢より20歳も30歳も年上の役を演じられる人がいるんです。声の質とか、見た目の印象だけでなく、演じられる役の幅が広いんですね。それは、もって生まれた才能と呼ぶべきものでしょう。
でも、僕にはそんな才能はなくて、いつでも等身大の年齢の役しか演じることができなかった。だから、40代の役を演じるには、自分が40代になるまで待たなきゃならなかったし、50代の役も、自分が50代になるまで演じられなかった。
そうやって、年をとって演じる役の幅を広げるための猶予期間を『世界の車窓から』が僕に与えてくれたのだと思うと、感謝してもしきれないですね。

「迷いの時期」を乗りこえて、50代は仕事が楽しくなった
2023年11月1日で石丸さんは70歳になります。これまでの俳優人生をふり返って、どんなことを思いますか?
石丸
つかさんのもとを離れてからの30代、40代は、「迷いの時期」でしたね。セリフがある役でも、主役の俳優さんのような量はありません。主演の俳優は、自分が納得する演技ができるまで議論したりできるけど、僕のようなチョイ役だと、監督が「はい、オッケー」と言えば、そのまま採用されてしまう。
そうすると、後になって「こうすればよかった、ああすればよかった」と反省することが多かったんです。実際、撮影所の近くの喫茶店で、僕と同じようなところでもがいている人がひとりでじっと一点を見つめていたりする姿を見ると、自分事のように思えたりしたものです。
だけど50代になると、悩んだり迷ったりすることも含めて、自分の仕事を楽しめるようになっていました。
仕事を楽しむには、どうすればいいのですか?
石丸
僕の場合、30代から40代の「迷いの時期」にたくさん失敗をしたおかげで、50代は自由に演技できるようになったことが大きいと思っています。
特に、2007年からの1年間、『仮面ライダー電王』(テレビ朝日系、佐藤健・主演)の現場は楽しかった。僕はここで、主役の仮面ライダー電王の行動を支持するオーナーと駅長の役をつとめました。
小道具係にクマちゃんと呼ばれるモノづくりの達人がいてね。休憩時間に「こんなの作ってよ」と、思いついたことを話すとその場でチャチャッと手を動かして、思い通りの小道具を作っちゃうんです。
例えば、一瞬でコーヒーカップが消える仕掛けだとかを作ってもらって、本番で披露してスタッフを驚かせるのが快感でね。
こういうアドリブは、役者的にはルール違反なんだけど、番組を見ている子どもたちには大いにウケていたようだから、これもよしと思ってね。さぁ、今日はどんな仕掛けをクマちゃんに頼もうかと、毎日ワクワクしながら撮影所に通っていました。
そんなふうに、スタッフの力を借りながら表現の幅を広げられたことで、仕事を楽しむ余裕ができていったんだと思います。


60歳を過ぎて、仕事は「おもしろい」ものに変わった
60代になってからは、何か変化がありましたか?
石丸
今度は仕事が、おもしろくなりました。
録音した自分の声を聞いたことがある人は、自分の声のように聞こえなくて違和感を感じることがあるでしょ?
それと同じように、自分が演じたシーンの映像をあとで見ると、それと同じような違和感があるんです。自分が演じたはずだと思っている自分と、映像に映っている自分との間にギャップを感じてしまう。
ところが60歳を過ぎると、そういう違和感がなくなっていきました。もちろん、あいかわらず「こうすればよかった、ああすればよかった」と反省することはあるんだけど、それでくよくよと悩むようなことはなくなりました。
同時に、これまで自分が出演したときの映像を再放送で見たりしても、「なかなかおもしろいじゃないか」と思えるようになりました。当時は「オレって演技が下手だなぁ」と落ち込んでた映像でも、60代になるとおもしろく見ることができるんです。
これは僕にとって、とてもうれしい変化でした。
70代になってからは、どんな変化がありそうですか?
石丸
これは、どんな仕事にも言えることだと思うけど、30代、40代の働き盛りのころと比べて、仕事というのはだんだんと減っていくものだと思うんです。
当然、70代からの僕の仕事も、50代、60代よりは少なくなっていくでしょう。
それは、仕方のないことで、悲しむべきことではありません。むしろ僕は、そのおかげで「趣味」の時間を増やすことができるので、ありがたいと思っているくらい。
だから、70代になったら、「仕事」と「趣味」の境界があいまいになっていって、どちらも同じようにおもしろがれるようになっているのが理想かな。
前編のインタビューの最後で、僕がいつも、20年後の自分を見ていることを想像するという話をしましたね。20年後の自分に対して、つねに「今がいちばん充実している」と言える自分でいたいですよね。
大変、励みになるお話、どうもありがとうございます!
石丸謙二郎の出版プロジェクト
「みなけりゃ分からない(みなわか)」シリーズ
敬文舎より好評発売中!
石丸謙二郎のエッセイの出版プロジェクトが、歴史書の刊行で有名な敬文舎とのコラボにより、「全10冊」を目指して進行中だ(既刊はいずれも税込価格1650円)。52歳から毎日欠かさず更新しているという膨大なブログの記事(すごい!)を再編集して大幅に加筆した珠玉のエッセイ。朋友・風間杜夫の「石丸の本は温かい。」の言葉に共感する人は、きっと多いに違いない。2023年秋には、第5弾の「みなわか」最新エッセイも刊行予定。乞うご期待!
『山は登ってみなけりゃ分からない』
登山歴50年を超える著者が山の魅力、おもしろきこと、めずらしき発見を楽しげに語る。NHKラジオ『山カフェ』のマスターが贈る、山好きによる山好きのための極楽エッセイ。

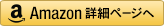
- 著者: 石丸謙二郎
- 出版社:敬文舎
- 発売日:2020年11月24日
- 定価:1,650円(税込)
『蕎麦は食ってみなけりゃ分からない』
蕎麦好きの人たちに、蕎麦の味わいを語るのがいかにむずかしいのか、その真髄に迫る。蕎麦の青春とは何か? 海外から帰ってきて最初に食べたくなるものは何か?

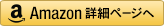
- 著者: 石丸謙二郎
- 出版社:敬文舎
- 発売日:2021年7月9日
- 定価:1,650円(税込)
『台詞は喋ってみなけりゃ分からない』
舞台、映画、ドラマなどでさまざまな役を演じてきた著者が、新たな視点で芝居を語る。虚構の世界の不可思議さなおもしろさを軽妙に語る傑作エッセイ。

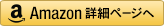
- 著者: 石丸謙二郎
- 出版社:敬文舎
- 発売日:2022年1月28日
- 定価:1,650円(税込)
『犬は棒にあたってみなけりゃ分からない』
電話に出た相手になぜ「いま大丈夫ですか?」というのか? 年配者はなぜ夜中に目が覚めるのか? など、日常生活の疑問の重箱を突つきながら語り尽くす、イシマル視点の痛快エッセイ。

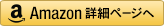
- 著者: 石丸謙二郎
- 出版社:敬文舎
- 発売日:2023年6月5日
- 定価:1,650円(税込)
この記事について報告する




