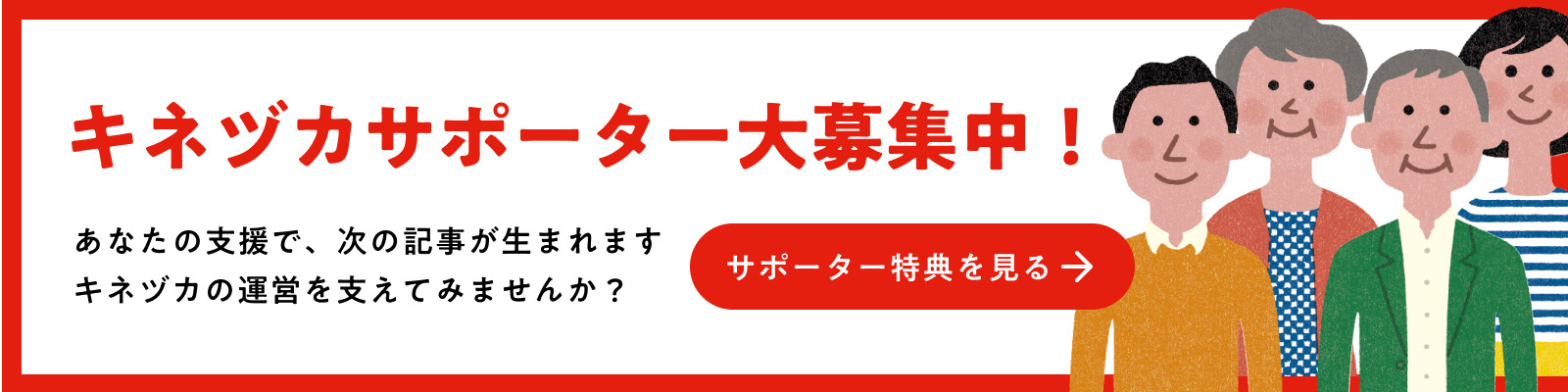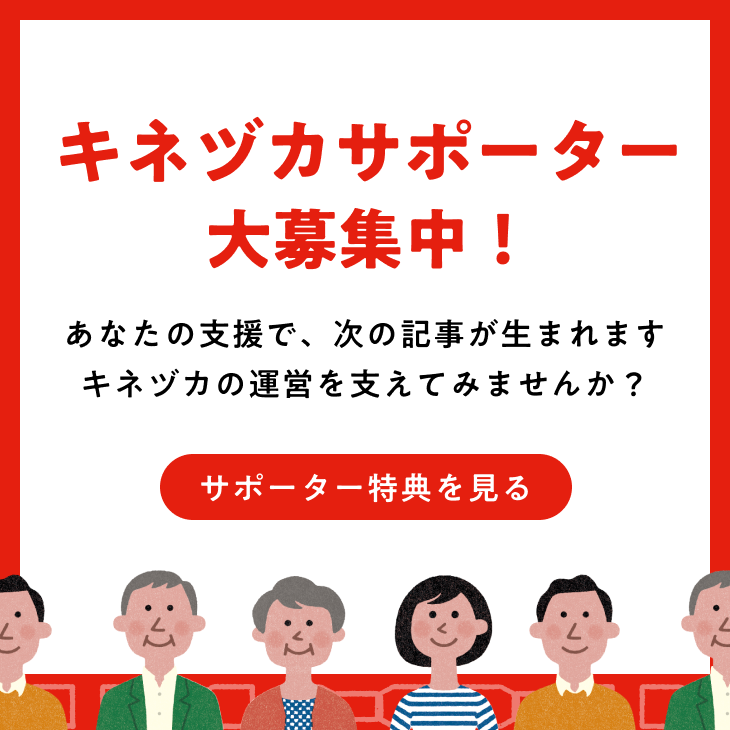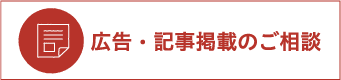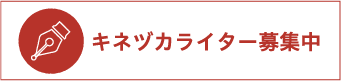介護のプランニング!介護支援専門員(ケアマネ)の資格

適切な介護サービスが受けられるようにケアプランを作成
高齢化社会の進行に伴い、介護に関する知識や技術を身に着けた人材の需要が高まっています。介護関連の専門職には、介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者(旧ホームヘルパー2級)などがありますが、介護支援専門員もそのうちのひとつです。
別名「ケアマネージャー」とも呼ばれ、2000年に「介護保険制度」が導入されたのと同時に生まれた職業です。要介護者が適切な介護サービスを受けられるように支援するのが主な役割で、具体的な仕事内容は要介護者やその家族、事業者、医療機関と相談してケアプランを作成したり、モニタリングやヒヤリングの結果を基に課題解決方法の検討を行ったりすることです。
事業者との契約、給与管理、要介護認定も仕事に含まれます。ケアマネージャーの業務範囲はあくまで介護のプランを作成して支援を行うことまでなので、実際の食事介助、入浴介助などの身体介護や、住居の掃除、食事の用意などの生活支援はホームヘルパーが行います。
ケアマネージャーになるのに年齢は関係ありませんが、資格を取得するには実務経験が必要なので平均年齢は44歳前後です。また、介護は長年の経験が生かされる仕事でもあるので、シニア世代が活躍できる職業でもあります。
2018年から受験資格要件が変更に
ケアマネージャーになるには、年1回10月に各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があります。試験を受けるには受験資格を満たさなければなりませんが、2015年に受験資格要件の見直しが行われ、要件がより厳しくなりました。
その内容は「国家資格(法廷資格)を所有し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上」または「相談援助業務に従事し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上」で、この2つのうちのどちらかを満たす必要があります。
2018年以降はこの新しい受験資格要件の下で試験を受けることになります。試験は全部で60問出題され、その内訳は介護支援分野が25問、保健医療サービス分野が20問、福祉サービス分野が15問です。全てマークシート形式で、7割以上が合格基準とされています。
試験の合格率、おすすめな勉強法は?
合格率は2004年頃までは30%程度でしたが年々下落傾向にあり、厚生労働省の発表によると2016年の合格率は13.1%です。受験資格要件の改定により今後も難化傾向が続き、さらに落ち込む可能性もあります。
記述試験はありませんが、試験範囲が広いのでしっかりとした対策をとる必要があります。独学での取得も可能で、その場合は効率良く勉強ができる通信講座を利用するのがおすすめです。
試験対策のスクールに通うという方法もありますが、講座によって受講期間が3カ月~6カ月とばらつきがあるので、自分の勉強スケジュールに合わせた講座を選択するのが良いでしょう。
あまり時間がとれないという人のために短期集中講座も用意されており、独学よりも短期間で試験対策ができます。模擬試験が受けられる点や仲間ができることによってモチベーションが維持できる点もスクールを利用するメリットとして挙げられます。
教育訓練給付金も活用できる!
なお、ケアマネージャーは一般教育訓練の教育訓練給付金対象講座に含まれているので、この制度を活用すれば受講費用の20%(上限10万円)を雇用保険から受給することができます。
資格試験に合格した後、15日間(87時間)の講義・演習と、居宅支援事業所での3日間の実習からなる実務研修を受けると、ケアマネージャーとして働けるようになります。
最新更新日 2018.05.29
関連キーワード
この記事について報告する