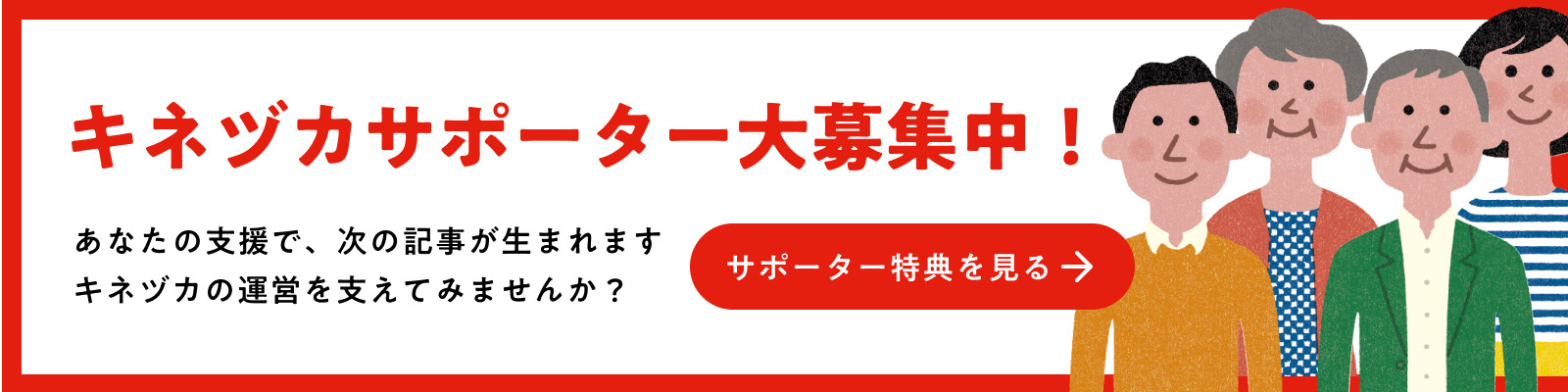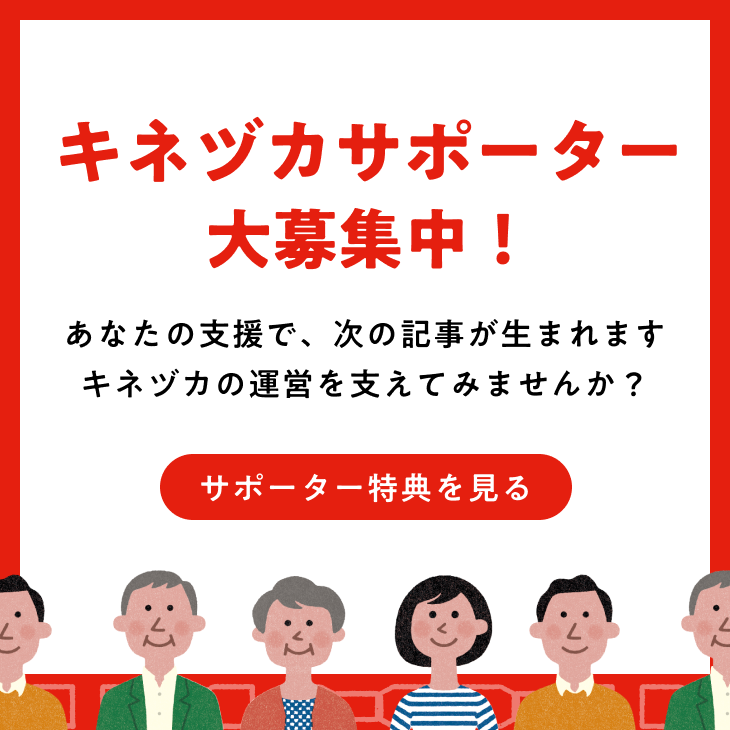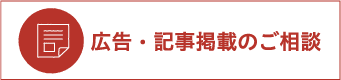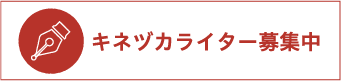認知症になる前に決めておきたい、後見制度

成年後見制度が守るもの
65歳~69歳の10人に1人、85歳以上の4人に1人――認知症の割合は高齢になるにつれて上がっていきます。認知症の進行は人によりさまざまで、詐欺などの犯罪のターゲットとなったり相続を含めた家族間のいざこざを招いたり、望まぬトラブルの原因となりかねません。
有効な対策はないのでしょうか?高齢者と家族の日々の生活や心身の健康を守るために公的な介護保険制度が存在しているように、高齢者の築き上げてきた資産や社会的存在としての尊厳を守る助けになるのが、成年後見制度です。
後見制度を履行することで、日常の買い物や預貯金の正当な管理など本人にとって利益となる契約を代行し、法外な商品代金などの不当な契約を取り消すことができます。
任意後見制度と法定後見制度
今すぐは必要ないけれど、将来的に判断能力にかげりが見えたときに備えておきたい。そんな場合、検討したいのは任意後見制度です。本人と支援者とであらかじめ支援内容を話し合い、二者間で任意に契約を結ぶことで、有事の際の対応がスムーズになります。
同じ任意後見制度でも、裁判所によって監査役もつけられる任意後見契約と、当事者間の委任契約に過ぎない任意代理契約とでは公正さの担保という意味で大きな違いがあるという点には注意が必要でしょう。
一方、認知症、知的障害、精神障害などの理由によりすでに判断能力が必要不十分であると認められた場合、申し立てを経て家庭裁判所によって選定された援助者が、財産の管理や煩雑な事務手続きなど生活面の支援を務めます。
これを法定後見制度と呼び、支援を必要とする人の判断能力のレベルに合わせて「補助人」→「保佐人」→「成年後見人」の順に職能が大きくなります。成年後見人と本人との関係は子が最も多く、以下に司法書士、弁護士と続きます。全体の約4割が親族、約6割が専門家である第三者となっています。
本人の保護とトラブル回避に役立つ一方、懸念されるのは職権の濫用による不正行為ですが、成年後見人は被後見人の財産を使用するに際しては詳細な記録を家庭裁判所に提出することが義務付けられており、使途不明金は厳格な指導・罰則の対象となるのです。
また、任意後見契約と同じく、家庭裁判所に申し立てることで、後見人の公正さを監督すべく後見監督人を選任することも可能です。
早めの検討が安心につながる
成年後見制度の申し立てには、本人と後見人候補者の戸籍謄本をはじめとする書類をそろえ、家庭裁判所を通じて手続きする必要があります。できる限り先延ばしにしたいのが人情ですが、判断能力が不十分と認定されてからでは、自分の後見人を自分で決めることは不可能になります。
さらに深刻なケースは、すでに認知症が始まっている方が遺産を相続する立場になったときです。認知症を患っている方は後見人の有無を問わず、法律行為である遺産分割協議に関わることができません。代行者たる法定後見人を持たない場合、諸般の手続きが遅れ相続税の申告期限を過ぎてしまうことも起こり得ます。
成年後見制度は、被後見人から自主性や権利を取り上げるものでは決してなく、必要なサポートを届けるためのシステムです。一生涯続く支援を誰からどのように受けるのか、本人と周囲、双方の安心のためにじっくりと話し合いましょう。弁護士事務所などの法律相談を利用するのもおすすめです。
最新更新日 2018.02.06
関連キーワード
この記事について報告する