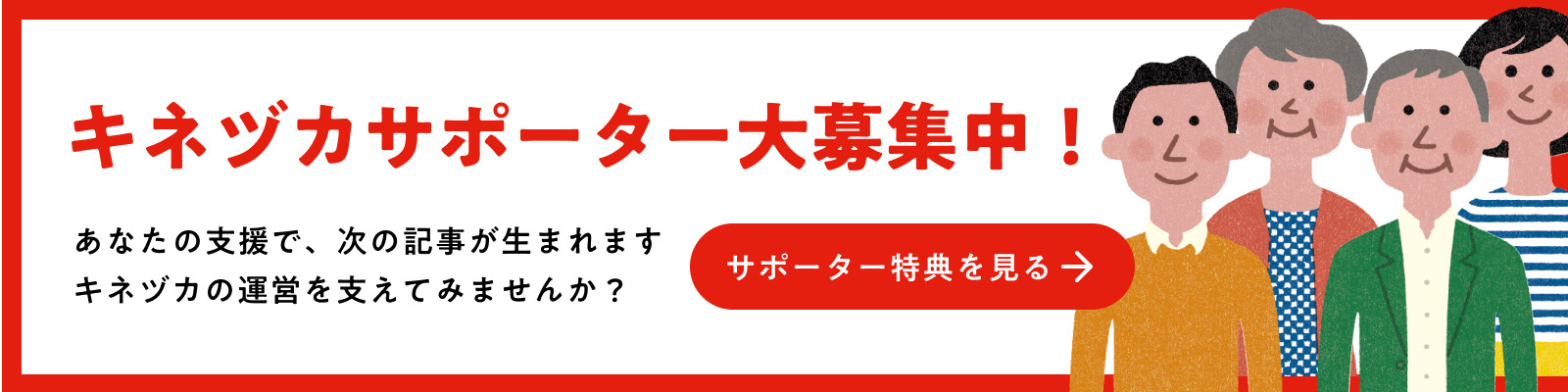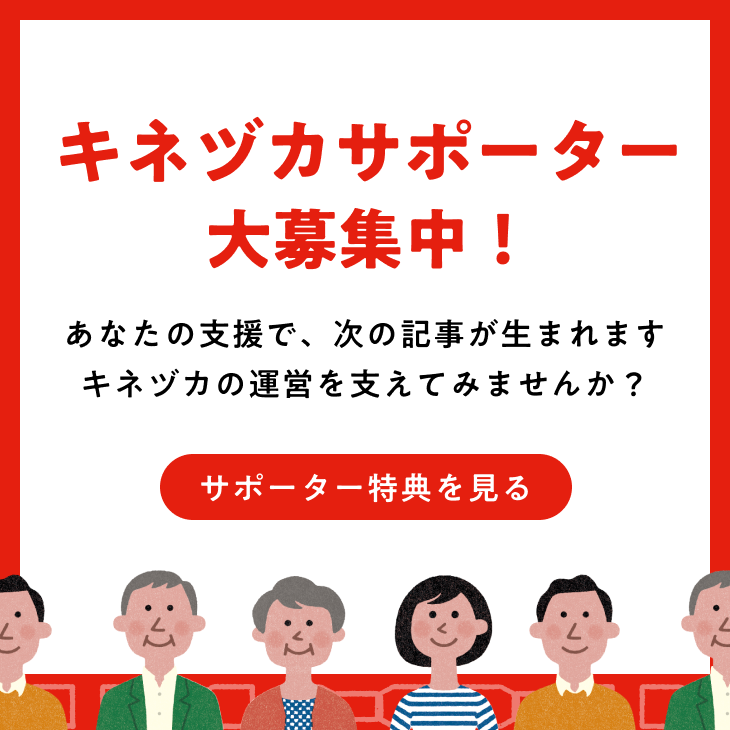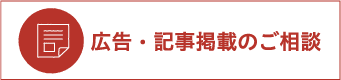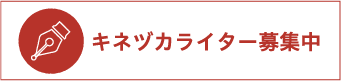外出するのに交通費は無料? 高齢者助成

知っておきたい交通費助成制度
「閉じこもり」という言葉をご存知でしょうか?高齢者が加齢に伴う心身の機能の低下をきっかけに自宅にこもりがちになる社会問題のことを指し、おおよそ外出の頻度が週に一度を下回るとその予備軍であると言われています。健康な生活を保つために、外出の習慣は欠かせません。
通い慣れた道を歩くのも運動にはなりますが、より刺激を求めるなら、遠方に足を伸ばすことも必要です。そこで気になるのは交通費です。シニアを対象とした各種の交通費助成制度を使いこなすことで、無駄なく交通機関を利用することが可能になります。
自治体によって多種多様……交通費助成の現状
高齢者の交通費助成制度として有名なのは、かつて都バスを無料で利用できた東京都のシルバーパスでしょうか。
現在では、住民税が非課税の70歳以上の都民であれば申請手続きと1,000円の自己負担で、都内で運行している乗り合いバスほぼすべてと、都電、日暮里・舎人ライナーなどの一部鉄道に乗車することができます。高速バスなど、特別料金の発生する交通機関には適用されません。
このように、敬老パスとして乗車証を発行するケースや、現金と併用する割引券が発券されるケース、割引料金対応のICカードが支給されるケースなど、自治体ごとに交通費助成の形態は大きく異なります。
対象年齢は70歳以上と定める場合が多く、65歳からの利用は名古屋市、堺市、大分市などごく一部の地域にとどまっています。
中にはシニア層の旅客を対象にした割引周遊パスは制度化されているものの住民に対する交通費助成は施行されていない自治体もありますから、お住まいの地域について調べる際は注意が必要です。
一律の規定が存在しないだけに、市区町村のカラーが色濃く反映されるサービスでもあります。奈良県生駒市の取り組みを例にとれば、交通費助成制度を単なる移動支援ではなく、総合的な生活支援の契機と捉え直す試みが行われています。
具体的には、介護支援サービスや健診費用・公共施設などの利用料金にも充填できるよう改善する、全国に先駆けたスタイルでの運営が検討されています。新制度が実用化されれば、他の自治体に同様の動きが広がることもあるでしょう。
お得にお出かけを楽しもう
交通費を完全に無料化することは難しいのが現状ですが、自分の年齢と居住地に照らした助成制度をきちんと把握し、活用することで、大幅なコストカットが可能です。お得な制度をぜひ利用して、時には知らない場所へ足を運んでみてはいかがですか?
趣味や会合、生涯の楽しみになる新しい出会いが待っているかも知れません。それはあなたの生活を豊かにするとともに、人が織りなす社会の輪ににぎわいを加える一助となることでしょう。
最新更新日 2018.02.08
この記事について報告する